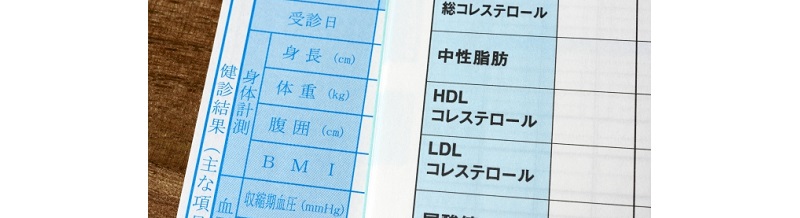一般社団法人 肥満予防健康協会が認定する民間資格で栄養、運動、生活習慣改善などに関する正しい知識をもとに、肥満の予防や健康管理をサポートできる人材を育成することを目的としています。
■主催
肥満予防健康協会
目次
受験資格と難易度
受験資格
特別な制限はなく、誰でも受験可能
- 年齢・性別・学歴・職歴の制限なし
- 初心者や医療・健康関連の資格を持っていない方もOK
- 講座受講者(通信・通学)のみ受験可能
→ 試験を受けるには、講座修了が必須条件
対象となる方の一例
- 健康やダイエットに興味がある一般の方
- フィットネストレーナー、ヨガインストラクター
- エステティシャン、介護職員、看護師、保健師など
- 家族の健康管理を学びたい主婦・主夫の方
難易度
比較的やさしめの民間資格
- 基礎的な健康知識・肥満対策の内容が中心
- 専門的な医学知識や統計学のような難解な問題は出題されない
- 公式テキスト・講義資料に沿ってしっかり学べば十分合格可能
試験の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験形式 | 筆記試験(選択式) |
| 試験時間 | 約60分 |
| 問題数 | 約40〜50問(年度により変動) |
| 出題形式 | 4択または5択の選択問題中心 |
| 合格基準 | 正答率おおよそ70%以上(公式には非公開) |
難易度の目安(5段階評価)
| 評価項目 | 難易度 |
|---|---|
| 知識の専門性 | ★★☆☆☆ |
| 学習時間の必要度 | ★★☆☆☆(10〜20時間程度) |
| 試験の合格率 | ★★★★☆(高め、受験者の多くが合格) |
| 初学者の対応しやすさ | ★★★★☆(独学でも取り組みやすい) |
試験内容
試験の概要
試験形式と時間
- 試験方式:筆記試験(選択式:マークシート形式)
- 試験時間:60分
- 問題数:約40〜50問(年度により変動あり)
- 問題形式:4択または5択の選択式問題
- 合格基準:正答率70%程度(公式な合格率は非公開)
出題内容(分野別)
試験では、講座内容に基づいた範囲から出題されます。主に以下のようなテーマが含まれます。1. 肥満の基礎知識
- 肥満とは何か(定義、BMIの計算方法)
- 肥満の種類(内臓脂肪型・皮下脂肪型)
- 肥満と健康リスク(糖尿病・高血圧・脂質異常症など)
2. 栄養と食事の管理
- 三大栄養素と五大栄養素の役割
- エネルギー収支(摂取エネルギーと消費エネルギー)
- 食生活改善(バランスのとれた食事・食事のタイミング)
3. 運動と活動量
- 有酸素運動と無酸素運動の違い
- メタボ予防のための運動習慣
- 生活の中での活動量アップの工夫
4. 行動変容とモチベーション支援
- 行動科学に基づく生活改善の支援法
- 継続的な目標設定とセルフモニタリングの手法
- 習慣化のサポート(リバウンド防止など)
5. カウンセリング・倫理
- クライアント対応の基本マナー
- 相手に寄り添った傾聴と助言の技術
- 健康情報を扱う際の個人情報保護や信頼関係の築き方
出題傾向と例題(参考イメージ)
出題傾向
- 講座内で扱った知識の理解度を問う問題が中心
- 暗記だけでなく、実生活に即した応用問題も含まれる
- 医学的・専門的な計算問題は少なく、基礎~実用レベル
例題イメージ(非公式)
問1:BMIが25以上30未満の場合、一般的にどのように分類されるか?- 低体重
- 標準体重
- 肥満(1度)
- 肥満(3度)
(正解:3)
- 骨粗鬆症
- 高血圧
- 脂質異常症
- 便秘
(正解:3)
出題割合(おおよその目安)
| 分野 | 出題比率の目安 |
|---|---|
| 肥満・健康の基礎 | 約25% |
| 食生活・栄養管理 | 約20% |
| 運動・身体活動 | 約20% |
| 行動変容・継続支援 | 約20% |
| カウンセリング・倫理 | 約15% |
試験対策
試験対策の基本方針
講座テキストをしっかり復習する
- 試験は講座で使用したテキスト・資料から出題される
- 講義資料内の用語、図表、表現などを繰り返し確認
- 暗記だけでなく「なぜそうなるのか」という理解ベースで学ぶ
模擬問題・確認テストを活用
- 通信講座・通学講座に付属している模擬問題集は必ず解く
- 間違えた問題を**「なぜ間違えたのか」まで見直す**ことが重要
- 時間を計って、本番と同じ環境で練習するのも効果的
分野別対策のポイント
1. 肥満の基礎知識
- BMI、肥満度分類、内臓脂肪と皮下脂肪の違いを正確に理解
- 肥満が引き起こす代表的な生活習慣病(糖尿病、高血圧など)との関係性もチェック
2. 栄養・食生活
- 五大栄養素の働き・エネルギー源としての役割を整理
- 摂取カロリーと消費カロリーの関係、エネルギーバランスの考え方をマスター
- 食事改善の実例を使って理解すると覚えやすい
3. 運動・身体活動
- 有酸素運動と無酸素運動の違い、それぞれの肥満改善への効果
- 「メッツ(METs)」「消費エネルギー」の基本計算も確認
- 日常生活での活動量アップ法(例:階段利用、家事)なども出題されることあり
4. 行動変容・生活改善支援
- 行動科学理論(例:ステージモデル、モチベーション維持法)を簡単に把握
- 習慣化のコツ、リバウンドを防ぐ心理的アプローチなどが出題されやすい
5. カウンセリング・コミュニケーション
- 傾聴、共感、フィードバックなどカウンセリングの基本姿勢
- クライアントへの伝え方や接し方に関する倫理的な判断も問われる
取得後に出来ること
肥満予防健康管理士取得後にできること
この資格は、肥満予防や生活習慣病対策の正しい知識を活かして、健康づくりの支援ができる人材として活躍することを目的としています。1. 健康アドバイザーとしての活動
- 一般の方やお客様に対して、肥満予防・生活改善のアドバイスが可能
- 健康相談会・地域イベントでの講師やブース対応スタッフとして参加
- 食事指導・運動提案・生活習慣改善のカウンセリング型支援
2. 職場でのスキルアップ・役割拡大
- フィットネスクラブ、スポーツジム、エステサロンなどでの専門性の高い接客に活かせる
- 医療・介護現場での利用者・患者の生活支援、指導補助
- 薬局・ドラッグストアなどでの生活習慣病予防商品の提案力が高まる
3. 転職やキャリアチェンジに活用できる
- 「健康支援ができるスタッフ」として、採用時のアピールポイントになる
- 医療・福祉・美容・スポーツ関連企業での職種に幅広く活かせる
- 地域密着型の健康支援事業(市民講座、行政主催イベントなど)にも参加しやすくなる
4. 家庭や地域での健康支援にも役立つ
- 家族の健康管理(高齢者の生活習慣改善や、子どもの食育など)に応用可能
- PTA・地域サークルでの健康講座や食生活勉強会の企画運営もできる
- 自分自身の体調・体重管理のスキルとしても効果的
資格を活かせる分野と職種
| 分野 | 活用例 |
|---|---|
| フィットネス | トレーナー、スタジオインストラクター、ジムスタッフ |
| 美容・エステ | カウンセラー、アドバイザー、施術者 |
| 医療・福祉 | 介護スタッフ、生活相談員、保健指導補助 |
| 健康関連販売 | サプリメント販売員、薬局・ドラッグストアスタッフ |
| 教育・地域活動 | 健康講座講師、生活改善セミナー主催など |
将来的なステップアップ
- 肥満予防健康管理士の上位資格である「肥満予防健康指導士」への挑戦
- 栄養士、健康運動指導士、食生活アドバイザーなど他資格との併用で専門性アップ
- 自身で健康講座を開いたり、地域活動の中心として活躍することも可能
その他医療系資格一覧
臨床心理士
精神対話士
生きがい情報士
認定心理カウンセラー
メンタルケア心理士認定試験
産業カウンセラー
メンタルヘルス・マネジメント検定試験
離婚カウンセラー
コンディショニングコーチ
肥満予防健康管理士
ヘルスケアアドバイザー
栄養情報担当者(NR)
運動療法士