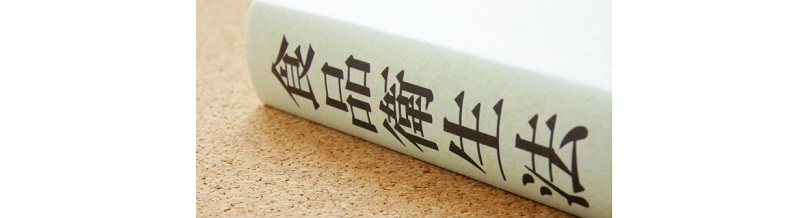飲食店や食品製造・販売施設などにおいて、食品の安全と衛生を確保するために必要な知識と責任を持つ者として、各施設に1名以上の配置が義務付けられている資格です。
■主催
(社)東京都食品衛生協会
受験資格と難易度
受講・受験資格
養成講習会の受講条件
- 年齢:原則として17歳以上
- 学歴・職歴:特に制限なし(高校卒業以上が望ましいが必須ではない)
- 居住地:基本的には都内在住または勤務者を対象にしているが、他都道府県在住でも受講可能なケースあり(要確認)
受講が不要な特定資格保有者
次のいずれかの資格を持っている方は、講習を受けずに食品衛生責任者としての届出が可能です。- 調理師
- 栄養士(管理栄養士含む)
- 製菓衛生師
- 船舶料理士
- 食品衛生監視員・食品衛生管理者の要件該当者
- 医師・歯科医師・薬剤師・獣医師
- と畜場法や食鳥処理法に基づく衛生管理責任者など
難易度
養成講習会の構成
- 時間:約6時間の講義(1日完結型)
-
内容:
- 衛生法規(食品衛生法や条例)
- 公衆衛生学(環境衛生・労働衛生)
- 食品衛生学(食中毒、施設衛生管理、HACCPなど)
- 確認テスト:講義内容の理解を確認する簡単なテスト
合格基準・難易度の実情
- 確認テストは講義中に強調された内容が中心
- **合格率はほぼ100%**とされ、落ちることはほとんどない
- 誰でも理解しやすい内容で、事前の特別な学習は不要
- 受講終了と同時に**「食品衛生責任者手帳」が交付**される
試験内容
養成講習会(約6時間)を受講し修了することで取得できます。実質的には「試験」と呼べるほどの難易度はなく、講習受講+簡単な確認テストという位置付けです。講習の構成(合計 約6時間)
1. 衛生法規(約2時間)
- 食品衛生法の概要
- 食品表示法との関係
- 営業許可制度・営業届出制度
- 管理運営基準(許可施設の基準)
- HACCPに沿った衛生管理の義務化
- 違反時の措置(営業停止・回収命令など)
2. 公衆衛生学(約1時間)
- 感染症とその予防
- ゴミ・排水などの環境衛生
- 作業環境の管理と従業員の健康管理
- 施設の設計と衛生的動線
3. 食品衛生学(約3時間)
- 食中毒の分類(細菌性、ウイルス性、化学物質など)
- 原因菌・ウイルスの特徴と対策
- 食品の取扱いにおける注意点
- 衛生的な調理・保存・運搬方法
- 食品の温度管理(加熱温度・保存温度の基準)
- 手指・器具・調理場の洗浄・消毒
- アレルゲン表示と食物アレルギーの管理
確認試験(修了テスト)
概要
- 実施時期:講習の最後に行われる
- 形式:10~20問程度の○×または簡単な選択式
- 出題内容:講習中に強調されたポイントが中心
- 合格基準:不合格者が出るような内容ではなく、講習を受けていれば解ける難易度
出題例(イメージ)
| 問題例 | 正誤 |
|---|---|
| ノロウイルスによる食中毒は冬に多く発生する | 正しい |
| 食品を加熱する際の中心温度は45℃が目安である | 誤り |
| 衛生管理計画の作成はHACCP制度化で義務となった | 正しい |
資格取得後の証明
- 確認テストに合格すると、「食品衛生責任者手帳」がその場で交付されます(※一部自治体は後日郵送)
- これにより、都道府県等の管轄保健所へ営業許可申請時に必要な要件を満たしたことの証明になります
講習の受講形式と選択肢
集合型講習(対面)
- 会場に集合し、1日かけて受講
- 講師による解説付きで分かりやすい
- 修了証はその場で交付
eラーニング型講習
- PCやスマートフォンで受講可能
- 自分のペースで視聴(途中で停止・再開OK)
- 視聴完了後に確認テストを受け、合格で修了
試験対策
講習(6時間)を受講することで取得できる講習修了型資格です。講習の最後に実施される「確認テスト」は難易度が低く、事前に過剰な勉強は必要ありませんが、講習を有意義にするための事前準備や講義中の姿勢が重要です。講習前にやっておくと良い準備
基本的な用語の事前チェック
-
食中毒の原因(細菌・ウイルス)
例:サルモネラ、カンピロバクター、ノロウイルス -
衛生管理の基本
手洗いの目的/調理器具の消毒方法/保存温度の基準など -
HACCP(ハサップ)とは何か?
衛生管理計画・記録の意義と義務化について、概念だけ把握しておくと理解が深まる
活用資料
- 東京都食品衛生協会のWebサイトにある**「受講前ガイドPDF」や「受講要領」**を確認
- 厚生労働省や保健所のサイトにある**HACCPリーフレット(図解付き)**もおすすめ
講習中の理解を深めるポイント
メモを取りながら聞くべき項目
- 講師が「ここ試験に出ます」と言った部分は確実にチェック
- **数字・基準値系の情報(加熱温度、保存温度、保存期間など)**は後の確認テストにも出やすい
- 表現の違い(例:「再加熱が必要」 vs 「常温保存可能」)に注意
質問時間の活用
- 不明点があればその場で質問しておくと、確認テスト前の理解度が安定する
- 他の受講者の質問から得られる情報も多い
確認テスト(修了テスト)対策
出題傾向
- 講習中に説明された内容がそのまま出題される
- **正誤問題・選択問題(10〜20問程度)**で構成されており、記述式はない
- 全問正解でなくても合格可能
よく出るテーマ
- ノロウイルスと手洗いの関係
- 調理器具や施設の消毒方法
- 食品の加熱温度(例:中心温度75℃以上で1分間以上など)
- HACCPにおける「CCP(重要管理点)」の意味
- 食品衛生法上の営業許可と責任者の配置義務
eラーニング受講時の注意点
- 映像視聴は途中で止めてもOKだが、再開忘れに注意
- 確認テストは1回のみ(再試験できないケースあり)なので確実に視聴後に挑戦
- メモやスクリーンショットで重要ポイントを残しておくと確認テストに有利
取得後に出来ること
飲食店や食品関連施設の営業許可に必須の法定資格であり、営業者(個人・法人問わず)または従業員の誰かが必ず1名以上取得している必要があります。資格取得により、食品を取り扱う事業の開始が法的に可能になります。1. 飲食店・食品関連施設での営業許可申請が可能になる
対象となる業種の例
- 飲食店営業(カフェ、レストラン、居酒屋など)
- 菓子製造業・惣菜製造業・パン製造業
- 弁当製造・仕出し業
- 食料品販売業(精肉・鮮魚など)
- 移動販売車での調理・販売
義務としての配置
- 食品衛生法により、営業許可が必要な業種では1施設につき1名の配置が義務化
- 経営者本人が資格を持つことも、従業員が資格を取得して代行することも可能
2. 自ら営業を始める(開業)が可能に
資格保持者としてできること
- 自宅やキッチンカーなどで飲食営業を開始(※営業許可が別途必要)
- イベント出店、フードフェスなどの一時営業許可申請にも対応
- 保健所への営業届出時に、資格者であることを証明できる
例:開業の具体的な場面
| 開業例 | 食品衛生責任者の役割 |
|---|---|
| カフェ開業 | 申請書類に責任者として氏名記載し、営業許可を得る |
| フードトラック | 衛生管理マニュアルを作成し、HACCP対応責任者として活動 |
| マルシェでの惣菜販売 | 販売方法・保存温度管理の指導と実行 |
3. 施設内の衛生管理の中心者として活動できる
日常業務での役割
- 従業員への衛生教育・手洗い指導
- 食品保管方法・調理器具の洗浄・消毒指導
- 異物混入、アレルギー対策などの衛生マニュアル管理
保健所対応もスムーズに
- 保健所からの立入検査の際に衛生管理計画や記録の説明を行う担当者になる
- 営業許可更新や改善命令対応時の法的窓口担当にもなる
4. 業界での信用力・雇用面での強み
採用・就職活動で有利に
- 小規模飲食店・食品販売店では即戦力として評価されやすい
- 「資格を持っている人を採用したい」と明示する求人も多数あり
- 飲食業界でのパート・アルバイト・副業でも待遇交渉がしやすくなる
副業・兼業にも活用可能
- 週末限定の移動販売
- 副業としての「間借りカフェ」や「料理教室」
- 飲食イベントへの出店などでも役立つ
5. 他の衛生資格との連携・ステップアップ
連携しやすい資格
- 調理師(食品衛生責任者資格を含む国家資格)
- 食品衛生管理者(大規模製造向け)
- 栄養士・製菓衛生師(届出により代替可能)
- 防火管理者や防災責任者と並び、施設運営における必須資格の1つ
ステップアップの方向性
- HACCPプランナー・食品衛生管理者への上位資格取得
- 食品表示検定など、品質・表示の専門家として活動領域を広げる
その他食品系資格一覧
食品衛生責任者
ふぐ調理師
すしエンターティナー
家庭料理技能検定
フードコーディネーター
カフェプランナー
雑貨カフェクリエイター
フードアナリスト
デザートクリエイター
惣菜管理士
ソムリエ
バーテンダー
ワインエキスパート
チーズプロフェッショナル
コーヒーコーディネーター
ティーインストラクター
ビアテイスター
紅茶コーディネーター
きき酒師
焼酎アドバイザー
日本茶インストラクター
中国茶認定初級インストラクター