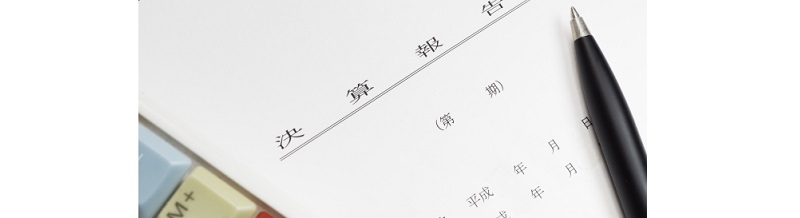企業や団体の財務・経理に関する専門的な知識を活かして、財務諸表の監査・保証業務、税務、経営コンサルティングなどを行う国家資格保有者です。
企業や組織の財務活動に関わり、監査やコンサルティング、税務支援などを通じて信頼性の高い経営をサポートする仕事で高い倫理観や専門知識が求められる職業で、企業の信頼性や透明性の確保に貢献しています。
受験資格と難易度
難易度:★★★★★
受験資格:特になし
受験データ
(1) 受験資格
日本では年齢や学歴による制限がなく、誰でも受験可能です。
(2) 試験内容
試験は3段階で構成されます:
- 短答式試験(マークシート形式)
- 論文式試験(記述式)
- 実務補習と実務経験(2年以上の実務経験)
科目には、会計学、監査論、財務管理、経済学、商法(会社法)などが含まれます。
試験場所:主要都市
■主催
公認会計士・監査審査会
試験について
公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験の2つがメインであり、その後に実務経験を積む必要があります。試験は難関ですが、しっかりと計画を立てて勉強することが合格へのカギです。
① 短答式試験
- 試験形式:マークシート形式
- 試験時期:年2回(5月・12月)
- 合格基準:総得点の70%以上
- 合格率:20~30%(論文式試験の受験資格を得るための第一関門)
出題科目
- 財務会計論(簿記・財務諸表の仕組み、基準など)
- 管理会計論(原価計算、意思決定支援など)
- 監査論(監査の目的、手続き、基準)
- 企業法(商法、会社法)
② 論文式試験
- 試験形式:記述式
- 試験時期:年1回(8月)
- 合格基準:科目ごとの基準点を満たし、総合点で合格ラインに達すること
- 合格率:10~15%(最終的な合格率)
必須科目
- 財務会計論(財務諸表作成、会計基準)
- 管理会計論(コスト管理、経営支援)
- 監査論(監査の計画、リスク評価)
- 企業法(会社法、商法)
- 租税法(法人税、消費税、所得税など)
選択科目(1科目選択)
以下のいずれか1科目を選択します。
- 経済学
- 経営学
- 民法
- 統計学
③ 実務経験
論文式試験に合格した後、2年以上の実務経験を積む必要があります。この実務経験は、監査法人、一般企業、税理士事務所などで行います。
実務補習も同時進行で受講し、最終的には「修了考査」に合格することで、公認会計士としての登録資格を得られます。
④ 勉強方法・試験対策
-
専門学校の活用
大手資格スクール(例:TAC、資格の大原、LECなど)では、公認会計士試験向けの講座が充実しています。独学が難しい場合、講座を受講することで効率的に学習できます。 -
学習時間の目安
合格までに必要とされる学習時間は、2,000~4,000時間といわれています。毎日3時間勉強した場合、約2~3年が目安です。 -
科目別対策
- 財務会計論・管理会計論:簿記や原価計算を徹底的に学ぶ
- 監査論:監査基準や事例を覚える
- 企業法:会社法の条文を理解し、事例問題に慣れる
- 租税法:税法の仕組みや計算問題を習得
⑤ 試験合格後のステップ
-
実務経験と補習修了
- 実務経験(2年以上)を積む
- 実務補習を受ける(日本公認会計士協会が主催)
- 最後に「修了考査」に合格
-
公認会計士登録
実務経験を終え、修了考査に合格した後、日本公認会計士協会に登録することで、正式に「公認会計士」として活動できます。
⑥ 試験の難易度
公認会計士試験は、日本国内でも最難関の資格試験の1つに位置付けられています。
特に、短答式試験・論文式試験の両方に合格するためには、計画的な勉強と継続的な努力が必要です。
公認会計士の給与や待遇
公認会計士の平均年収は600万~1,000万円以上で、経験年数や勤務先によって大きく異なります。特に監査法人のパートナー(経営者的立場)になると、数千万円規模の収入を得ることもあります。
試験対策
① 試験全体の学習計画
- 学習期間:2~3年が一般的
- 目標時間:2,000~4,000時間(1日3~4時間ペースを継続)
- フェーズごとの学習目標
- 1年目:基礎固め(簿記・財務会計、会社法などの理解)
- 2年目:短答式試験対策と応用問題練習
- 3年目:論文式試験対策と過去問演習
② 科目別対策
1. 財務会計論(簿記・財務諸表分析)
ポイント
- 公認会計士試験の中心科目。ここを制することが合格のカギ。
- 簿記と会計基準の理解が必須。
対策
- 日商簿記2級・1級レベルの知識を身につける
- 会計基準(収益認識基準、リース会計、減損会計など)を覚える
- 過去問や予想問題を繰り返し解き、計算スピードを向上させる
2. 管理会計論(原価計算・意思決定会計)
ポイント
- 原価計算の仕組みや意思決定に必要なデータ分析が重要。
対策
- 原価計算の基本パターン(標準原価計算、直接原価計算)を理解
- CVP(損益分岐点分析)や差額原価分析などの応用問題を解く
- 実務事例を意識し、計算問題に慣れる
3. 監査論
ポイント
- 理論的な内容が多いため、暗記だけでなく理解が求められる。
- 監査の目的、手続き、監査基準の理解が不可欠。
対策
- 「監査基準」や「リスク・アプローチ」の内容をしっかり理解
- 監査手続き(計画立案、実施、意見表明)の流れを覚える
- 過去問を使い、論述の練習を行う
4. 企業法(会社法・商法)
ポイント
- 法律系の科目。条文の暗記に加え、事例問題を解く力が必要。
対策
- 会社法(株主総会、取締役会、企業組織再編)を中心に学ぶ
- 条文を参照しながら、過去問を解く
- 事例問題に対する論述力を磨く
5. 租税法
ポイント
- 税金の計算問題が中心。特に法人税・消費税の理解が重要。
対策
- 法人税、所得税、消費税の基本的な計算ルールを理解
- 税務申告書の作成手順を把握
- 過去問で税法特有のひっかけ問題に慣れる
③ 短答式試験対策
- 出題範囲が広いため、網羅的な学習が必要
特に、財務会計論・管理会計論・監査論に重点を置いて学習。 - マークシート形式のため、計算問題をスピーディーに解けるよう訓練する。
- 模試を定期的に受験して、弱点を把握する。
④ 論文式試験対策
- 記述式問題の練習を重視
記述力(要点を整理して書く力)を鍛えるため、過去問や模試を活用する。
具体的な対策
-
答案構成の練習
問題文を読み、問われている内容に対して簡潔に答えられるようにする。 -
模範解答を研究
解答例を分析し、合格者の答案と自分の答案を比較。論述のコツを学ぶ。 -
時間管理
試験当日は時間との戦いになるため、時間内に答案を仕上げる練習を積む。
⑤ 実務補習の準備
論文式試験合格後、実務補習で学ぶ内容(監査手続き、企業法関連事例など)を意識しながら勉強しておくと、実務にスムーズに移行できます。
⑥ 勉強方法の工夫
- アウトプット重視:テキストを読むだけではなく、計算・記述問題を解いて理解を深める。
- 専門学校の講座活用:資格学校(TAC、大原、LECなど)の講座は試験対策に特化しているため、独学が不安な場合におすすめです。
- 過去問分析:10年分程度の過去問を分析し、出題傾向を把握する。
おすすめの講習、教材
 教材
教材
 講座
講座
財務・経営系資格一覧
公認会計士
税理士
中小企業診断士
簿記検定
ファイナンシャル・プランニング技能士
証券アナリスト
簿記能力検定
建設業経理検定
経営士
ファイナンシャル・プランナー
実用数学技能検定
DCプランナー
DCアドバイザー
マーケティング・ビジネス実務検定
MBA
不動産証券化協会認定マスター
モーゲージプランナー
銀行業務検定試験
BATIC(国際会計検定)
CPA(米国公認会計士)
米国公認管理会計士
米国税理士(EA)
PMP試験
CISA(公認情報システム監査人)
CIRP(サーティファイド・IRプランナー)
シニアリスクコンサルタント
ITコーディネータ資格認定制度
ファイナンシャル・リスクマネージャ
アクチュアリー資格試験
二種外務員資格試験
CIA(公認内部監査人)
CFA(CFA協会認定証券アナリスト)
ホスピタリティ検定試験
イベント業務管理者
ファシリティマネージャー
PRプランナー資格認定制度
プロジェクトマネジメント資格
VEリーダー認定試験
販売士検定
セールススキル検定試験
セールスレップ資格認定制度
販路コーディネータ資格認定制度
交渉アナリスト
CISM(公認情報セキュリティマネージャー)