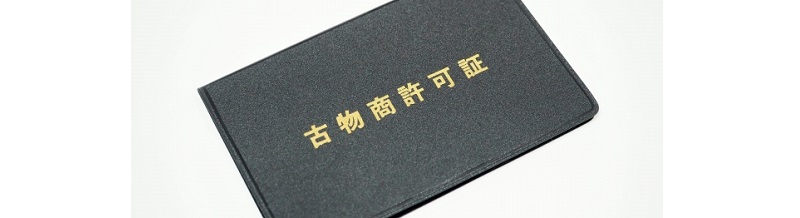日本で古物(中古品)を売買、交換、貸出を行う事業を行うために必要な資格です。
この資格を取得することで、古物の取引が法的に認められます。古物商の業務は「古物営業法」によって規定されており、無許可で古物取引を行うと罰則が科せられます。
古物商が扱う「古物」の定義
古物営業法では、古物は「一度使用された物品、または使用されなくても取引されたことがある物品」と定義されています。主な古物の分類は以下の通りです。
- 美術品類(絵画、彫刻など)
- 衣類(中古の服やバッグ)
- 時計・宝飾品
- 自動車・自動二輪車およびその部品
- 書籍
- 家具・家電
- 楽器
- 工具
- 玩具・ゲーム類
古物商資格が必要なケース
以下のような場合に古物商資格が必要です。
- 中古品を仕入れて販売する場合(フリマアプリで継続的に販売する場合も含む)
- リサイクルショップを開業する場合
- 中古車販売業を行う場合
- 古物を買い取って修理・再販売する場合
例外: 個人的に使用していた物を不定期に売る場合や、贈与・処分目的で販売する場合は資格不要です。
目次
受験資格と難易度
受験資格
古物商資格を取得するためには、特別な学歴や試験は必要ありません。しかし、古物営業法に基づき、以下の条件を満たしていることが必要です。
受験(申請)資格の主な条件
-
年齢制限:
- 申請者は 20歳以上 であること。
-
欠格事由がないこと:
以下のいずれかに該当する場合、申請はできません。- 禁錮以上の刑を受けてから5年以内の者
- 暴力団関係者またはその関係が疑われる者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年以内の者
- 心身の故障により業務遂行が困難な場合
-
営業所の確保:
日本国内に実体のある営業所が必要です。自宅でも問題ありませんが、実際に事業が行われることが条件です。 -
法人の場合:
- 代表者・役員全員が上記の欠格事由に該当しないこと。
- 定款の目的に「古物営業」が含まれていること。
難易度について
試験の有無
古物商資格取得に試験はありません。申請書類の提出と警察による審査で許可が下りる仕組みです。
難易度の実情
- 取得の難易度: 低
正しい書類を用意し、欠格事由に該当しなければほとんどの人が取得できます。 - 主な難関:
- 必要書類の準備(不備があると審査が遅れる)
- 住民票や身分証明書の取得時の細かい条件(本籍記載・マイナンバー除外など)
- 営業所の確保(実体のないバーチャルオフィス不可)
審査期間
通常、申請から許可まで30日程度かかります。申請に不備がなければスムーズに進みますが、書類不備があると再提出になり、期間が延びます。
試験内容
古物商許可を取得する際には、試験はありません。
古物商資格は「申請制」であり、学力テストや筆記試験、実技試験を受ける必要はありません。取得のためには、必要な書類を提出し、警察署の審査を受けるのみです。
審査で確認される主なポイント
試験はありませんが、申請後の審査で以下のポイントが確認されます。
1. 欠格事由の有無
申請者(個人・法人役員)が以下に該当しないかを審査します。
- 過去5年以内に禁錮以上の刑罰を受けたことがあるか
- 暴力団関係者でないか
- 過去に古物商許可を取り消されていないか
- 営業能力や事業遂行能力に支障がないか
2. 営業所の実態確認
- 営業所が実在し、古物取引を実施できる環境であることを確認。
- バーチャルオフィスやレンタル住所のみでは不可。
3. 必要書類の正確性
- 提出書類に虚偽がないか確認。
- 住民票や身分証明書、登記簿謄本の内容が正しいか。
古物営業法に関する知識の必要性
試験はないものの、古物営業法の知識は重要です。
古物商許可取得後は、以下の法律やルールを遵守する必要があります。
必須知識項目
- 古物台帳への記録義務
- 顧客の本人確認方法(特に10万円以上の取引時)
- 許可証の携帯義務(出張買取時など)
- 標識掲示のルール
- 警察からの要請への対応方法
試験対策
取得する際には試験はありませんが、許可取得後に法律を遵守して営業するために、古物営業法の知識が必須です。
営業中に法律違反があると、行政処分や罰則を受ける可能性があるため、試験はないものの自主的な学習が重要です。
古物営業法に関する必須知識と対策
1. 古物台帳の記載ルール
- 記載義務: 古物を買い取る際は、取引内容を「古物台帳」に記録する必要があります。
- 記載内容:
- 買い取った日時
- 商品の詳細(種類・特徴)
- 相手方の氏名・住所
- 確認した身分証明書の種類と番号
対策:
- 古物営業法の条文を確認しておき、台帳の記載例を参照する。
- 警察署や業界団体が提供するサンプル台帳で練習する。
2. 本人確認義務の理解
- 10万円以上の現金取引では、顧客の本人確認が必須です。
- 本人確認方法: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの提示を受けること。
対策:
- 確認対象となる取引額や身分証明書の種類を覚える。
- 実際の確認フローをイメージして、顧客対応時に迷わないようにする。
3. 標識掲示義務のポイント
- 営業所には「古物商標識」を掲示する必要があります。
- 標識には許可番号・氏名(または会社名)・許可を出した公安委員会名が記載されます。
対策:
- 標識の掲示場所(顧客が見やすい位置)や作成方法を確認。
4. 許可証の携帯と提示義務
- 出張買取や移動販売時には、許可証を携帯し求めがあれば提示する義務があります。
対策:
- 許可証携帯義務のある場面を確認し、外出時のルールを把握する。
5. 盗品防止のための対応
- 警察から盗難品の照会があった場合、迅速に対応する必要があります。
- 不審な商品や顧客からの取引依頼は断ることが重要です。
対策:
- 商品仕入れ時の確認ポイントをまとめ、不審取引への対応例を考えておく。
取得後に出来ること
取得すると、日本国内で合法的に中古品(古物)の取引を事業として行うことが可能になります。この許可は、買い取り、販売、交換、レンタルといったさまざまな形態の古物取引に対応しています。
1. 中古品の買い取りと販売
出来ること
-
中古品を仕入れて販売
- 個人や企業から中古品を買い取り、店頭やオンラインで販売が可能。
- フリマアプリで継続的に販売する場合も許可が必要。
-
リサイクルショップの運営
- 中古家具、衣類、家電などを取り扱う店舗を開業できる。
-
ネットオークションやECサイトでの販売
- Amazon、楽天、ヤフオク、メルカリなどでの中古品販売が可能。
許可がないとできないこと
- 営利目的で中古品を仕入れて販売する行為。
- 定期的にフリマアプリで中古品を販売すること(無許可は違法)。
2. 中古品の交換・レンタル事業
-
古物の交換事業
- 中古品同士の交換サービスを運営できる。
-
レンタル業務
- 買い取った古物をレンタル用として提供できる。
- 例:中古家電や工具のレンタルサービス。
3. 出張買取・宅配買取サービス
- 顧客の自宅を訪問して中古品を買い取るサービスが可能。
- 宅配で送ってもらった商品を査定し、買取するビジネスも許可内で実施できる。
4. 古物市場(オークション)への参加
- 古物商のみが参加できる業者専用オークションに参加可能。
- より安価で仕入れができ、仕入れ先の選択肢が広がる。
5. 中古品の輸出入(条件付き)
- 古物商許可を持つことで、中古品の海外輸出・輸入が可能。
- 注意: 国によっては輸入規制や許可が別途必要。
6. 委託販売や代理販売
- 他人から預かった中古品を代わりに販売することが可能。
- 古物商として信頼性が高まり、委託ビジネスも展開しやすくなる。
7. ブランド品や貴金属の取り扱い
- 高額なブランドバッグ、時計、貴金属などの中古品取引が可能。
- 適正な本人確認を行うことで、高額取引も安全に実施できる。
8. 自動車やバイクの中古販売
- 車両系古物の取扱い:
- 中古自動車・オートバイを買い取り、販売が可能。
- 別途、陸運局での手続きが必要な場合もある。
古物商許可を取得してもできないこと(注意事項)
- 新品のみの販売には不要:
新品商品のみを取り扱う場合は古物商許可は不要。 - 違法な商品の取引:
偽ブランド品、盗品、著作権侵害商品は厳禁。 - 不正な本人確認の省略:
一定額以上の取引では顧客の身元確認が必須。