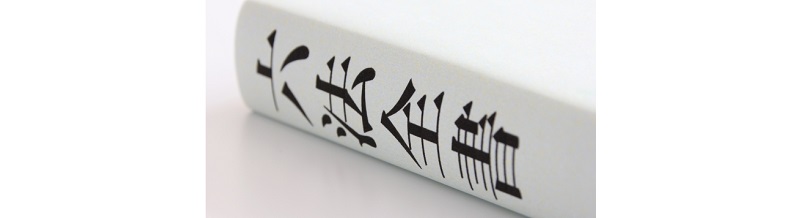法学の基礎から応用までの知識を測定する検定試験で、法律を学ぶ学生や社会人向けの資格です。法律の知識を体系的に学ぶことができ、企業法務や行政関連の業務にも活用できます。
試験の概要
(1) 実施団体
- 日本評論社 法学検定試験委員会
- 法学検定試験運営委員会
- 法律学を体系的に学ぶ機会を提供し、法学の知識を客観的に評価するための試験を実施
(2) 試験の目的
- 法律学の基礎から応用までの知識を証明
- 企業や公務での法務対応力の向上
- 法学を学ぶ学生の学習の進捗確認
- 法曹を目指す人の基礎力向上
目次
受験資格と難易度
1. 受験資格
- 受験資格に制限なし
- 年齢、学歴、職業などの制限はなく、誰でも受験可能
- 法律を学びたい学生、社会人、法務担当者、公務員志望者などが対象
- 法律初心者から上級者まで、レベルに応じた受験が可能
2. 難易度
法学検定試験には3つのレベル(ベーシック・スタンダード・アドバンスト)があり、それぞれの難易度が異なります。
(1) ベーシック(基礎)
難易度: 易しい(初学者向け)
- 合格率: 70~80%(比較的高め)
- 必要な学習時間: 約50~100時間
(2) スタンダード(中級)
難易度: 標準(法律を学んだ人向け)
- 合格率: 50~60%(やや難易度高め)
- 必要な学習時間: 約100~200時間
(3) アドバンスト(上級)
難易度: 難しい(専門家レベル)
- 合格率: 30~40%(難関)
- 必要な学習時間: 約300~500時間
3. 難易度比較表
| レベル | 難易度 | 合格率 | 学習時間の目安 | 出題内容 |
|---|---|---|---|---|
| ベーシック | 易しい | 70~80% | 約50~100時間 | 法学の基礎(憲法・民法・刑法など) |
| スタンダード | 標準 | 50~60% | 約100~200時間 | 実務的な法学知識(六法全般・判例) |
| アドバンスト | 難しい | 30~40% | 約300~500時間 | 実務レベルの法律応用(訴訟法・経済法など) |
試験内容
「ベーシック(基礎)」「スタンダード(中級)」「アドバンスト(上級)」**の3つのレベルがあります。それぞれの試験内容について詳しく解説します。
1. 試験範囲(全レベル共通)
法学検定試験では、法律の基本となる「六法」を中心に出題され、上級になるほど専門的な分野が追加されます。
| 分野 | 内容 |
|---|---|
| 憲法 | 日本国憲法の基本原則、人権保障、統治機構(国会・内閣・裁判所) |
| 民法 | 契約、物権、親族・相続、債権・不法行為 |
| 刑法 | 犯罪の成立要件、刑罰の種類、正当防衛・過失・未遂など |
| 商法(会社法含む) | 会社の種類、取締役・株主総会の権限、企業法務の基本 |
| 行政法 | 行政手続、行政救済、国家賠償法 |
| 民事訴訟法 | 訴訟の流れ、証拠、判決の確定と執行 |
| 刑事訴訟法 | 刑事事件の流れ、逮捕・起訴・裁判の手続き |
| 労働法 | 労働基準法、労働契約法、労働組合法 |
| 知的財産法(上級のみ) | 特許権・商標権・著作権の保護制度 |
| 経済法(上級のみ) | 独占禁止法、不正競争防止法 |
| 環境法(上級のみ) | 環境保護に関する法律(環境基本法、公害防止法) |
| 租税法(上級のみ) | 所得税法、法人税法、消費税法 |
2. レベル別 試験内容の詳細
(1) ベーシック(基礎レベル)
試験概要
- 試験時間: 90分
- 問題数: 約50~60問
- 出題形式: 多肢選択式(4択)
- 合格基準: 正答率60%以上
出題内容
| 分野 | 出題ポイント |
|---|---|
| 憲法 | 基本的人権、統治機構(国会・内閣・裁判所の役割) |
| 民法 | 契約の基本(売買・賃貸借)、親族・相続の基礎 |
| 刑法 | 犯罪の成立要件(故意・過失)、刑罰の種類 |
| 商法 | 会社の種類(株式会社・合同会社など)、企業の基本ルール |
| 行政法 | 行政の役割、行政手続の基本 |
| 訴訟法(民事・刑事) | 訴訟の流れ、裁判の手続き |
特徴
- 法律初心者向けの内容
- 条文の基本知識を問う問題が中心
- 難易度は低めで、法学入門者でも対策しやすい
(2) スタンダード(中級レベル)
試験概要
- 試験時間: 120分
- 問題数: 約80問
- 出題形式: 多肢選択式(4択)
- 合格基準: 正答率60%以上
出題内容
| 分野 | 出題ポイント |
|---|---|
| 憲法 | 違憲審査制、判例の知識、人権保障と制約 |
| 民法 | 契約の無効・取消、債権譲渡、時効、抵当権・担保制度 |
| 刑法 | 犯罪の共犯、未遂と既遂の違い、特別法犯罪 |
| 商法 | 会社の機関、株主総会・取締役の権限、企業の契約 |
| 行政法 | 行政処分、行政救済制度(取消訴訟・国家賠償請求) |
| 訴訟法(民事・刑事) | 訴訟の進め方、判決・控訴・上告の仕組み |
| 労働法 | 労働契約、解雇規制、労働組合の権利 |
特徴
- 大学法学部レベルの内容
- 判例をもとにした応用問題が増える
- 企業法務や公務員試験対策にも役立つ
(3) アドバンスト(上級レベル)
試験概要
- 試験時間: 150分
- 問題数: 約100問
- 出題形式: 多肢選択式+記述式
- 合格基準: 正答率70%以上
出題内容
| 分野 | 出題ポイント |
|---|---|
| 憲法 | 重要判例(猿払事件、薬事法事件)、統治機構の問題 |
| 民法 | 契約の詳細、賠償責任、遺言・相続の高度な内容 |
| 刑法 | 正当防衛と過剰防衛、詐欺罪・横領罪の区別 |
| 商法 | M&A、会社の合併・分割、株式市場のルール |
| 行政法 | 行政不服審査制度、行政機関の責任 |
| 訴訟法(民事・刑事) | 証拠の評価、上告・再審制度 |
| 労働法 | 労働争議、団体交渉の仕組み |
| 知的財産法 | 特許権・商標権の具体的な適用事例 |
| 経済法 | 独占禁止法、不正競争防止法 |
| 環境法 | 環境アセスメント制度、公害防止法 |
| 租税法 | 税務訴訟、所得税・法人税の計算方法 |
特徴
- 司法試験・公務員試験レベルの知識が必要
- 実務に基づいた事例問題・判例問題が中心
- 記述式問題が含まれ、論理的な法的思考が求められる
試験対策
1. 共通の試験対策
(1) 出題範囲を把握する
- 公式テキストの内容を確認し、六法を中心に出題される分野を整理
- 試験レベルごとの範囲を理解し、学習計画を立てる
(2) 公式テキスト・問題集を活用
- **日本評論社の「法学検定試験 公式テキスト」**を使用
- 過去問を徹底的に解く
- 頻出問題を優先的に学習
- 出題形式に慣れ、解答スピードを上げる
(3) 判例の学習
- 特に中級(スタンダード)以上は判例の知識が重要
- 憲法・民法・刑法などの重要判例を整理し、結論と論点を理解
2. レベル別の試験対策
(1) ベーシック(基礎レベル)対策
対策ポイント
基本知識の理解を徹底
- 憲法・民法・刑法を中心に、基本用語・概念を整理
- 法律の条文を正しく理解し、用語を暗記
過去問演習で試験形式に慣れる
- 4択問題のため、頻出問題を繰り返し解く
- 間違えた問題は、なぜ間違えたかを確認する
おすすめ教材
- 「法学検定試験 公式テキスト(ベーシック)」
- 「法学入門」系の参考書(初学者向け)
(2) スタンダード(中級レベル)対策
対策ポイント
条文・判例の理解を深める
- 六法全書を活用し、条文の意味を正確に理解
- 判例の結論と論点を整理し、法律の適用を学ぶ
事例問題の演習
- 実務的な法律問題が出題されるため、事例問題に慣れる
- **「契約の有効性」「賠償責任」「犯罪の成立要件」**など、応用力を鍛える
おすすめ教材
- 「法学検定試験 公式テキスト(スタンダード)」
- 「基本判例解説」シリーズ(憲法・民法・刑法)
- 「法律事例演習書」(大学の法学部向け教材)
(3) アドバンスト(上級レベル)対策
対策ポイント
司法試験・公務員試験レベルの学習が必要
- 記述式問題が出題されるため、論述力を養う
- 具体的な判例の結論とその理由を説明できるようにする
企業法務・実務的な法律知識を学ぶ
- 会社法・労働法・知的財産法・租税法などの専門分野を重点学習
- 契約書の解釈・行政手続の実務など、実際の法律適用を意識する
おすすめ教材
- 「法学検定試験 公式テキスト(アドバンスト)」
- 「判例六法」シリーズ(学習用)
- 「論述対策」用の法律問題集(司法試験・行政書士試験向け)
3. レベル別 直前対策
(1) ベーシック(試験1週間前)
公式テキストの総復習(憲法・民法・刑法を重点的に)
過去問を解き直し、苦手分野を整理
重要な法律用語・概念を暗記
(2) スタンダード(試験1週間前)
重要な判例・条文を復習(特に憲法・民法・刑法)
過去問を時間を計って解く(時間配分の練習)
事例問題の解答の仕方を確認
(3) アドバンスト(試験1週間前)
記述式問題の最終確認(論理的な解答を作成する練習)
重要判例の判旨を再確認
模擬試験を実施し、試験時間内に解答できるか確認
4. 試験対策のポイントまとめ
| 対策項目 | ベーシック | スタンダード | アドバンスト |
|---|---|---|---|
| 基本知識の学習 | 必須(基礎を固める) | 必須(判例の理解が重要) | 必須(深い理解が求められる) |
| 過去問演習 | 重要(出題形式に慣れる) | 重要(事例問題の練習) | 重要(記述式対策) |
| 判例学習 | 必須(基礎レベル) | 重点的に(憲法・民法・刑法) | かなり重要(判例の論点整理) |
| 論述問題対策 | なし | 軽め | 必須(記述式問題あり) |
取得後に出来ること
取得すると、法律の基礎から実務応用までの知識があることを証明でき、企業の法務部門、公務員試験、法律系資格試験の準備など、幅広い分野で活用できます。以下、レベル別に取得後の活用方法を解説します。
1. 企業・ビジネス分野での活用
(1) 企業の法務部門での業務
契約書の作成・審査
- スタンダード・アドバンストレベル取得者は、契約書のリーガルチェックができる
- 企業間の取引契約、労働契約、ライセンス契約などの基本理解がある
コンプライアンス(法令遵守)業務
- 企業が法的リスクを回避するための社内規定作成に関与
- 知的財産権、労働法、独占禁止法などの基本知識を活かせる
労務管理・人事の法的対応
- 労働基準法や労働契約法に基づき、労働環境の適正化に貢献
- 解雇・残業代・ハラスメント対応など、実務で活かせる知識が得られる
活躍できる職種:
- 法務部門(契約管理・コンプライアンス担当)
- 人事・総務部門(労務管理)
- 企業のリスクマネジメント担当者
(2) 企業の知財・マーケティング分野
知的財産権の管理(商標・特許・著作権)
- アドバンストレベル取得者は、企業の知的財産管理に関与
- 広告・マーケティング部門で、著作権や商標権を適切に扱う
SNS・広告運用時の法的リスク管理
- 著作権侵害・肖像権のトラブルを回避し、適法なコンテンツを運用できる
- インフルエンサーマーケティングや動画コンテンツ作成時のガイドライン作成に活用
活躍できる職種:
- 知的財産管理(企業の知財担当者)
- 広告・マーケティング(SNS運用・ブランド戦略)
2. 公務員・行政関連での活用
(1) 国家公務員・地方公務員試験の準備
法律科目の強化
- 行政法・憲法・民法・刑法の基礎が身につくため、公務員試験の法律科目対策に有利
- 特にスタンダード・アドバンストレベル取得者は、公務員試験(地方上級・国家総合職・法律職)の基礎知識を固められる
行政手続・法令適用の実務
- 行政法・地方自治法の知識を活かし、条例作成や行政指導の対応ができる
- 住民対応、規制緩和、法律に基づいた政策立案が可能
活躍できる職種:
- 国家公務員(法務・行政系)
- 地方公務員(市役所・県庁の法務部門)
- 警察・司法関連(法務局・裁判所職員)
(2) 行政書士・社労士・司法書士試験の基礎固め
法律系資格試験の基礎学習に役立つ
- 行政書士・社会保険労務士・司法書士試験における六法(憲法・民法・行政法・労働法)の学習に直結
- スタンダード・アドバンストレベル取得者は、法律系資格試験の初学者よりも有利なスタートが切れる
3. 司法試験・法律専門職のキャリア
(1) 司法試験・予備試験の準備
司法試験受験者の基礎知識強化
- 法学検定のアドバンストレベルを取得すると、司法試験の憲法・民法・刑法・行政法・商法の基礎が身につく
- 基本判例や条文の適用力が試されるため、司法試験の短答式試験の対策にもなる
弁護士・司法書士・行政書士の実務補助
- 企業法務、M&A、知的財産関連のリーガルチェックを担当
- 訴訟対応、契約交渉の補助業務ができる
活躍できる職種:
- 司法試験受験生(基礎固め)
- パラリーガル(法律事務所の補助業務)
- 法律専門職(弁護士・司法書士・行政書士のアシスタント)
4. 法学検定取得後のキャリアアップ
(1) 転職・キャリアアップに有利
企業法務・知財部門への転職
- 法務・コンプライアンス職の求人で有利に
- スタンダード以上の資格を持っていると、法律知識があることをアピール可能
公務員試験の法律職
- 法学検定の学習経験があると、法律職の公務員試験で優位
- 事前知識を持っていることで、公務員試験の合格可能性が高まる
(2) フリーランス・独立で活かす
契約書作成・リーガルチェック業務
- フリーランスのクリエイターやコンサルタントが、契約書の基本を理解できる
- クライアントとの契約交渉において、適切な契約条項を把握し、トラブル回避が可能
法律講師・研修講師
- 企業の法務研修、コンプライアンス研修の講師として活躍
- 法律入門セミナーを開催し、副業・独立の道を開くことも可能
5. 法学検定取得後にできることのまとめ
| 活用分野 | 具体的な活用内容 |
|---|---|
| 企業法務 | 契約書作成・リーガルチェック、コンプライアンス業務 |
| 知的財産 | 商標・特許・著作権の管理、SNS・広告法務 |
| 公務員試験 | 国家公務員・地方公務員(法律職)、法令適用・行政手続業務 |
| 法律資格試験 | 行政書士・司法書士・社労士試験の基礎固め |
| 司法試験対策 | 司法試験・予備試験の基礎学習 |
| 転職・キャリアアップ | 企業の法務部門への転職、公務員試験の法律科目対策 |
| フリーランス | 契約書作成、コンプライアンスコンサルタント、法律講師 |
司法・法務系資格一覧
司法書士
行政書士
知的財産管理技能検定
弁理士
社会保険労務士
通関士
海事代理士
ビジネス著作権検定
法学検定試験
ビジネス実務法務検定
ビジネスコンプライアンス検定
個人情報保護士認定試験
企業情報管理士認定試験
個人情報保護法検定
貿易実務検定
米国弁護士
貿易スペシャリスト認定試験
認定コンプライアンス・オフィサー(CCO)
認定プライバシーコンサルタント